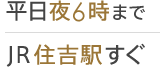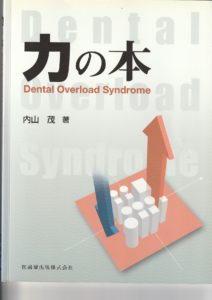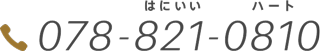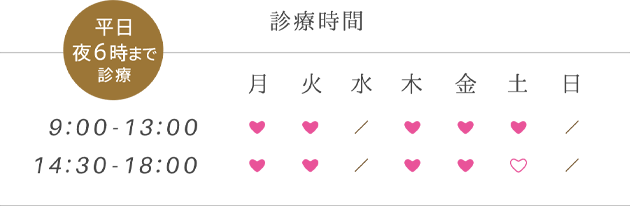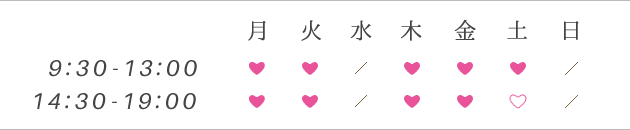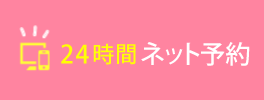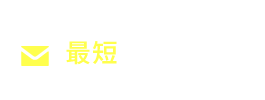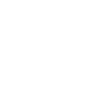こんにちは。
神戸市東灘区住吉にあります、おおにしハート歯科 歯科衛生士の竹中です。
肌寒い日が増えてきましたが、いかがお過ごしでしょうか🌤
前回は、唾液の役割について紹介しました。
今回は、唾液の「質」について紹介します。
唾液には水分としてだけではなく体を守るいくつもの物質(成分)が含まれています。
口は体の「外」から「中」への入り口です。空気中には細菌やウイルスがたくさんいますし、食べ物には体に害のあるものも紛れ込んでいるかもしれない。そんな外敵から体を守る重要な役割を唾液は担っています。
今回紹介するネバネバ唾液(粘液性唾液)に含まれるムチンは食べ物を飲み込みやすくし、喉に流してくれます。アミラーゼは糖を分解します。カルシウムは脱灰から歯を守り、唾液由来タンパク質であるペリクルも歯を守っています。他にもたくさんの成分が含まれていて私たちの口腔と全身を守っています。


・抗菌・免疫作用
IgG(免疫グロブリンG)とおなじく抗体であるIgA(免疫グロブリンA)は口腔粘膜表面にあり、外から入ってくるウイルスなどを攻撃できるので、生体に入る前の門番のような役割を果たしています。唾液には、このIgAが豊富に含まれています。IgAと相乗効果を示すリゾチームやラクトフェリンにも感染を阻止する物質が認められます。リゾチームは細菌の持つ細胞壁を構成する物質を分解することで、細菌が機能できなくなるようにします。ラクトフェリンは、細菌の生存に必要な鉄を細菌から奪い取ることで、その活動を停止させます。ウイルスが生体に結合するのを阻止することもあります。その他、ペルオキシターゼ、シスタチン、アミラーゼも抗菌作用があります。
・緩衝作用
普段の唾液の酸性度は平均約㏗6.8の弱酸性です。就寝時は唾液量が激減するのでより酸性に傾きますが起床すれば中性に向かいます。安静時唾液に比べ、刺激性唾液は酸性に傾いた㏗を中性に戻す力がはるかに強いのですが、これは唾液中に重炭酸塩という物質が含まれているからです。この重炭酸塩によって酸性に傾く口腔内を中性に戻すことができます。これを唾液の緩衝能といいます。重炭酸塩の量が多い人は酸性状態が継続する時間が短くなるのでう蝕(むし歯)のリスクは低くなります。
・再石灰化作用
発酵性炭水化物(主に砂糖)の摂取により、プラーク(磨き残し)が酸性に傾く結果、歯は溶け、う蝕(むし歯)になります。また、酸性飲食物の摂取によっても歯は溶け、酸蝕になります。唾液中に含まれるカルシウムやリンによって、う蝕(むし歯)や酸蝕が阻まれます。歯の構成成分であるカルシウムやリンが外に出ようとしても、外側の唾液にカルシウムやリンが多くあるので、外に出られないということです。もちろん、酸による脱灰により歯の成分の一部が溶け出してしまうこともあります。でも、プラークが中性に戻れば、唾液中にあるカルシウムやリンが奪回した病巣に戻ります。これが再石灰化です。しかし、う窩になって歯に穴が空いてしまうと足場がなくなるのでその場所が元に戻ることはありません。ごく初期の脱灰であれば、唾液中に含まれるカルシウムやリンが病巣に戻ることで、ほぼ元通りになります。
もちろん酸性状態を中和して中性に戻すのは唾液の緩衝作用で、酸性状態を希釈して薄めるのは唾液の「水分」としての作用です。
睡眠中や安静時は唾液の分泌が少なくなるので細菌がより活発になります。
これらのことから、水を摂取するより唾液を分泌させることが重要になるのです。
参考文献:歯科衛生士(クインテッセンス出版) 2023.3月号